
日建設計総合研究所(NSRI)は、都市計画マスタープランの策定を数多くの都市において手掛けているほか、立地適正化計画、駅周辺をはじめとした地区まちづくり計画など、地方公共団体等が策定する様々な計画や都市政策の立案に関わっています。それらの多くに携わってきた藤田主任研究員にお話を聞きました。
都市計画マスタープランとは
倉石: 都市政策グループの役割について教えてください。
藤田: 長期的な視点での都市の将来像を構想し、その実現のための基本的な方針を示す都市計画マスタープランをはじめ、行政計画や都市政策に関する、調査・企画・コンサルティングが主な役割です。地方公共団体等からの依頼により、日建グループならではの具体の都市空間に対する提案力や表現力を活かしながら政策立案の支援を行っています。
倉石: 藤田さんはこれまで渋谷区や江東区をはじめとした特別区や、政令指定都市等の都市計画マスタープランの立案に携わってきたとのことですが、都市の将来像を考えるというのは、どのようなプロセスになるのでしょうか?
藤田: 作業手順やマニュアルとして示すのは難しいのですが、関連する行政計画や市民ワークショップでの意見などを拠り所にしながら、地域らしさを言葉にし、将来像としてとりまとめていく作業を行います。
倉石: 都市ごとの一品生産ということなのですね。
藤田: まち歩きのようなミクロな経験も含め、地域らしさや地域の固有性は非常に重要な視点です。一方で、都市計画マスタープランは区市町村単位の計画ですから、その範囲を超えた広域的な視点が見過ごされがちです。周辺の自治体を含めた広い範囲での施設立地やインフラの状況、将来に予想される変化から、当該自治体がどのような位置づけにあり、今後どのような役割が期待されているのかを読み解くことも求められています。
藤田: 長期的な視点での都市の将来像を構想し、その実現のための基本的な方針を示す都市計画マスタープランをはじめ、行政計画や都市政策に関する、調査・企画・コンサルティングが主な役割です。地方公共団体等からの依頼により、日建グループならではの具体の都市空間に対する提案力や表現力を活かしながら政策立案の支援を行っています。
倉石: 藤田さんはこれまで渋谷区や江東区をはじめとした特別区や、政令指定都市等の都市計画マスタープランの立案に携わってきたとのことですが、都市の将来像を考えるというのは、どのようなプロセスになるのでしょうか?
藤田: 作業手順やマニュアルとして示すのは難しいのですが、関連する行政計画や市民ワークショップでの意見などを拠り所にしながら、地域らしさを言葉にし、将来像としてとりまとめていく作業を行います。
倉石: 都市ごとの一品生産ということなのですね。
藤田: まち歩きのようなミクロな経験も含め、地域らしさや地域の固有性は非常に重要な視点です。一方で、都市計画マスタープランは区市町村単位の計画ですから、その範囲を超えた広域的な視点が見過ごされがちです。周辺の自治体を含めた広い範囲での施設立地やインフラの状況、将来に予想される変化から、当該自治体がどのような位置づけにあり、今後どのような役割が期待されているのかを読み解くことも求められています。

コンパクトシティに向けた取組み
大石: コンパクトシティは、近年の都市計画においても大きなトレンドになっているのでしょうか。
藤田: 人口減少下にある近年では、生活拠点などに生活利便施設や住宅を集約し、公共交通と連携してまちづくりを進める「コンパクト+ネットワーク」といった意味で使われています。
大石: コンパクトシティはどのように実現されるのでしょうか?
藤田: 立地適正化計画を策定することにより、都市全体の構造を見渡しながら都市機能や居住の誘導と、それと連携した公共交通ネットワークの再編に取り組むことができます。とはいえ、住民の皆さんに今住んでいる場所から移ってもらうのはすぐには難しいことです。
大石: 居住の誘導が難しい、という事実は、水害の懸念のある河川近くの住宅地など、災害リスクを抱えている地域では深刻な課題になりそうですね。
倉石: 加えて、最近は都市のスポンジ化の課題もよく耳にします。
藤田: 市街地の中に空き地、空き家・空き室が増えるスポンジ化という現象は、地方都市に限らず大都市でも進行が懸念されています。住宅の量は充足していますが、マンションなど新築のニーズが強く、それが既存ストックの活用を妨げているという背景もあります。
倉石: どれが空き家なのか、また空き家の持ち主は誰なのかという実態把握が難しい点も、既存ストックの利用が進まない理由の一つかもしれませんね。ただ空き家が増えている感覚は私の住んでいる地域でもあるので、身近な都市問題として感じます。
藤田: 人口減少下にある近年では、生活拠点などに生活利便施設や住宅を集約し、公共交通と連携してまちづくりを進める「コンパクト+ネットワーク」といった意味で使われています。
大石: コンパクトシティはどのように実現されるのでしょうか?
藤田: 立地適正化計画を策定することにより、都市全体の構造を見渡しながら都市機能や居住の誘導と、それと連携した公共交通ネットワークの再編に取り組むことができます。とはいえ、住民の皆さんに今住んでいる場所から移ってもらうのはすぐには難しいことです。
大石: 居住の誘導が難しい、という事実は、水害の懸念のある河川近くの住宅地など、災害リスクを抱えている地域では深刻な課題になりそうですね。
倉石: 加えて、最近は都市のスポンジ化の課題もよく耳にします。
藤田: 市街地の中に空き地、空き家・空き室が増えるスポンジ化という現象は、地方都市に限らず大都市でも進行が懸念されています。住宅の量は充足していますが、マンションなど新築のニーズが強く、それが既存ストックの活用を妨げているという背景もあります。
倉石: どれが空き家なのか、また空き家の持ち主は誰なのかという実態把握が難しい点も、既存ストックの利用が進まない理由の一つかもしれませんね。ただ空き家が増えている感覚は私の住んでいる地域でもあるので、身近な都市問題として感じます。
住民参加の方法
藤田: 都市計画マスタープランは、都市計画やまちづくりの基本的方針を示すという性格から抽象的になりがちです。一方で、住民の地域への想いや課題を反映することも重要です。
倉石: 住民参加ですね。どのように地域の皆さんから意見を集めるのでしょうか?
藤田: 住民の主体的な参加を募り、共同作業をしたり対話をしながらファシリテーターが意見をまとめていくワークショップの開催が一般的です。コロナ禍においてはオンラインによる参加手法も試みていますが、活発な意見交流を生むためには、参加の臨場感・リアル感が重要であることが分かってきました。VR(バーチャル・リアリティ)、補助用のデジタルツールなどの活用方法の進展が課題です。
倉石: ワークショップでは、参加人数が限られており、住民を代表する意見が得られないという批判もあると思います。
藤田: 住民の意見を収集するため、無作為抽出によるアンケート調査で統計的な有意性を担保し、その上でワークショップを行うケースがほとんどです。住民参加のアウトプットを行政計画にどのように擦り合わせるかは大きな課題ですが、ワークショップは熟議の場であり、その結果である集合的な創造性は、デジタル時代において一層意義が深まると考えています。
倉石: 住民参加ですね。どのように地域の皆さんから意見を集めるのでしょうか?
藤田: 住民の主体的な参加を募り、共同作業をしたり対話をしながらファシリテーターが意見をまとめていくワークショップの開催が一般的です。コロナ禍においてはオンラインによる参加手法も試みていますが、活発な意見交流を生むためには、参加の臨場感・リアル感が重要であることが分かってきました。VR(バーチャル・リアリティ)、補助用のデジタルツールなどの活用方法の進展が課題です。
倉石: ワークショップでは、参加人数が限られており、住民を代表する意見が得られないという批判もあると思います。
藤田: 住民の意見を収集するため、無作為抽出によるアンケート調査で統計的な有意性を担保し、その上でワークショップを行うケースがほとんどです。住民参加のアウトプットを行政計画にどのように擦り合わせるかは大きな課題ですが、ワークショップは熟議の場であり、その結果である集合的な創造性は、デジタル時代において一層意義が深まると考えています。

プロジェクト実現型のプランへ
大石: 都市計画マスタープランは抽象的である、というお話しがありましたね。
藤田: 従来の都市計画マスタープランは「絵に描いた餅」と呼ばれるなど抽象的・総花的であることが多かったのですが、それを克服すべく実効性の高いマスタープランを模索しています。
大石: 従来の都市計画マスタープランとの違いはどのようなものでしょうか?
藤田: 都市開発のポテンシャルが大きい都心部などでは、長期的・網羅的な視点をもったマスタープランはあまり役には立ちません。状況がすぐに変化してしまうからです。そこで、特定のプロジェクト、例えば多様な主体が関わる都市開発プロジェクトを重点施策に位置付け、その実現化の方策を示すとともに、行政がリーダーシップを発揮して促進するための方針を示すプロジェクト型のプランが考えられます。
倉石: 重点施策の実現を目指す、という観点からは、都市計画マスタープランにKPI(目標に対する達成の度合いを測るための指標)を設定するという流れもありそうですね。
藤田: 基本的な方針を示す計画であることから、KPIのような数値目標の設定はなじまないとされてきました。しかし、実効性の高いプランとするためには、KPIの設定は避けられないと思います。
大石: 歴史ある都市計画マスタープランですが、計画の性格が変化しつつあるということですね。
藤田: 従来の都市計画マスタープランは「絵に描いた餅」と呼ばれるなど抽象的・総花的であることが多かったのですが、それを克服すべく実効性の高いマスタープランを模索しています。
大石: 従来の都市計画マスタープランとの違いはどのようなものでしょうか?
藤田: 都市開発のポテンシャルが大きい都心部などでは、長期的・網羅的な視点をもったマスタープランはあまり役には立ちません。状況がすぐに変化してしまうからです。そこで、特定のプロジェクト、例えば多様な主体が関わる都市開発プロジェクトを重点施策に位置付け、その実現化の方策を示すとともに、行政がリーダーシップを発揮して促進するための方針を示すプロジェクト型のプランが考えられます。
倉石: 重点施策の実現を目指す、という観点からは、都市計画マスタープランにKPI(目標に対する達成の度合いを測るための指標)を設定するという流れもありそうですね。
藤田: 基本的な方針を示す計画であることから、KPIのような数値目標の設定はなじまないとされてきました。しかし、実効性の高いプランとするためには、KPIの設定は避けられないと思います。
大石: 歴史ある都市計画マスタープランですが、計画の性格が変化しつつあるということですね。
渋谷ならではのカルチャーをまちに展開
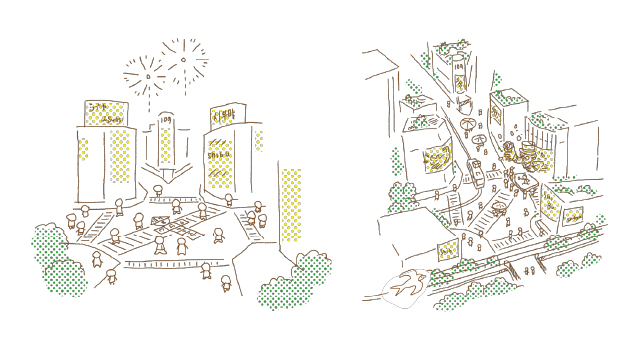
様々な視点を行き来するアプローチ
藤田: 行政計画は課題を解決する方策であることから、課題ありきとなるきらいがあり、また、有用と無駄を分けるなど複雑なものを単純化しようとする傾向があります。一方、本来の都市とは、地域らしさが偶然に形成されるなど、複雑なものです。都市を使う者、楽しむ者として、既存の枠組みを疑い、見えない問題を探索することが都市のあり方を考える態度ではないかと考えています。
倉石: 都市の本質を探ろうとする態度や虫の目、鳥の目の視点があり、様々な都市の見方を行き来した上で、都市政策へアプローチされていることが良く分かりました。本日はどうもありがとうございました。
倉石: 都市の本質を探ろうとする態度や虫の目、鳥の目の視点があり、様々な都市の見方を行き来した上で、都市政策へアプローチされていることが良く分かりました。本日はどうもありがとうございました。




