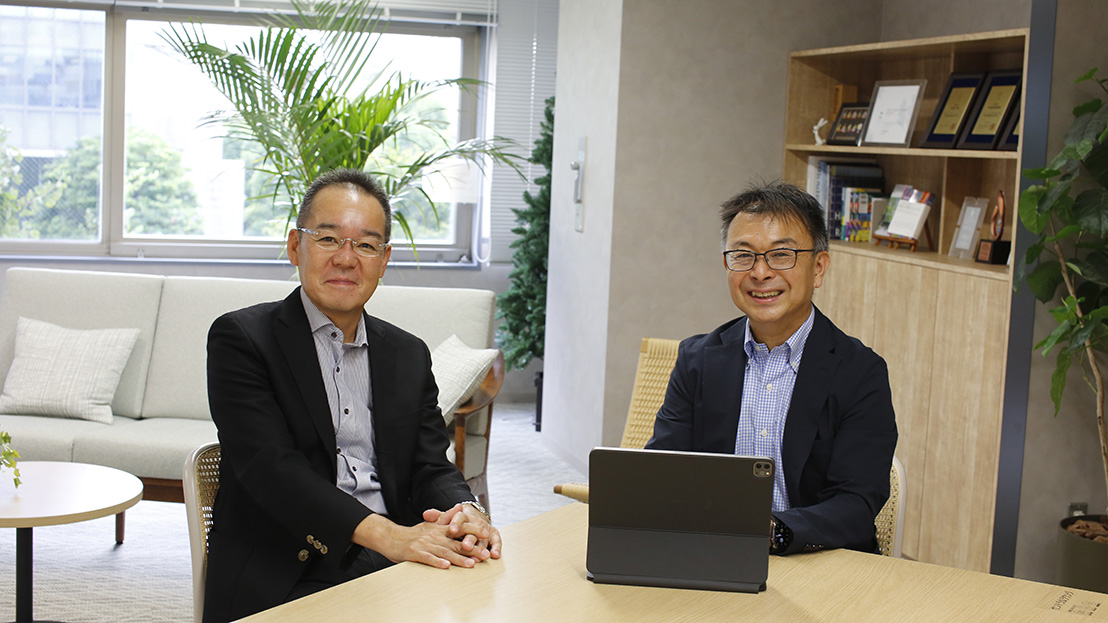日建設計総合研究所では、ビッグデータやAIを活用したまちづくりや不動産DXに積極的に取り組んでいます。これらの最新テクノロジーが爆発的な進化を続けている今、不動産情報の高度化をはじめ、この領域のソリューションサービスは一段と重要性を増しています。一橋大学 社会科学高等研究院 都市空間不動産解析研究センター長の清水千弘教授をお迎えし、役員・主席研究員の川除隆広が、都市の不動産市場動向と不動産DXの可能性についてお話を伺いました。
規制緩和で都市の一等地が“暮らす場”に
川除: 清水先生は不動産経済学を長年ご研究されています。まずは長期トレンドの中で、都市の不動産市場がどのように変わってきたとお考えでしょうか。
清水: 「都市は誰のものか」という問いが昔からあります。都市の主役は、時代の移り変わりと共に交代してきました。戦後の高度経済成長期は、産業の発展を支える工場が都市の中心部を占めていたのです。やがて産業構造が変わり、1980年代にはサービス業、情報通信業など第三次産業の割合が増加します。すると、オフィスビルが工場よりも高い収益性を持つようになり、都心は企業の“働く場”としての性格を強めました。そして今、その都心にタワーマンションが次々に建設されるようになり、再び様変わりしています。

川除: タワーマンションが増え始めたきっかけは、やはり2002年の「都市再生特別措置法」施行でしょうか。
清水: そうですね。規制緩和政策によって増えたタワーマンションは、高層ゆえにオフィスビルと競争できるほどの収益性を持つようになりました。それで、かつては工場やオフィスしか建てられなかった都心に人が住めるようになったのです。都市の一等地が“暮らす場”として開放された、歴史的な大転換だと言えます。実際、東京都心の千代田区、中央区、港区は2000年代以降、夜間人口が大幅に増加しています。タワーマンションの価格は高すぎるという批判がありますが、建物の耐震性や断熱性が格段に向上し、ジムの併設やコンシェルジュの常駐など、高品質なサービスが提供されているのだから、高価格は妥当との見方もできます。これは経済学的にも「ヘドニック価格理論」で裏付けられますね。
川除: なるほど。都心部の住宅価格高騰は、地価上昇や投機だけでなく、住宅そのものの“質的改善”も大きな理由だということですね。ところで、海外ではオフィス需要が減少し、空室率が高まっているという話を耳にします。この状況は日本のオフィス市場にどう影響しますか。
清水: そうですね。規制緩和政策によって増えたタワーマンションは、高層ゆえにオフィスビルと競争できるほどの収益性を持つようになりました。それで、かつては工場やオフィスしか建てられなかった都心に人が住めるようになったのです。都市の一等地が“暮らす場”として開放された、歴史的な大転換だと言えます。実際、東京都心の千代田区、中央区、港区は2000年代以降、夜間人口が大幅に増加しています。タワーマンションの価格は高すぎるという批判がありますが、建物の耐震性や断熱性が格段に向上し、ジムの併設やコンシェルジュの常駐など、高品質なサービスが提供されているのだから、高価格は妥当との見方もできます。これは経済学的にも「ヘドニック価格理論」で裏付けられますね。
川除: なるほど。都心部の住宅価格高騰は、地価上昇や投機だけでなく、住宅そのものの“質的改善”も大きな理由だということですね。ところで、海外ではオフィス需要が減少し、空室率が高まっているという話を耳にします。この状況は日本のオフィス市場にどう影響しますか。
今後ますます“都市の多機能化”が進む
清水: 企業の立場からすれば、最も生産性の高い形で活動することが重要です。コロナ禍のロックダウンを経て、在宅勤務が効率的だと広く認識されるようになったのが、海外のオフィス需要減少の一因だと思われます。日本の企業には、まだオフィスに集まる働き方を好むマネジメント層が残っていますが、世代交代と共に日本でも従業員の幸福度を含む“生産性の高い働き方”が主流になるでしょう。
川除: そうなった時、オフィスが都市の一等地を占め続ける必要があるのか疑問ですね。同じエリアに同種企業が集まることで経済的なメリットが生じるという「集積の経済」は今後どうなりますか。
川除: そうなった時、オフィスが都市の一等地を占め続ける必要があるのか疑問ですね。同じエリアに同種企業が集まることで経済的なメリットが生じるという「集積の経済」は今後どうなりますか。

川除: 働く、住む、集う、楽しむといった多様な機能が都心に集まることで、平日の昼間だけでなく、夜間や休日も活気のある、24時間魅力的な空間が生まれているわけですね。都市の魅力が増した日本への不動産投資額が継続的に上昇しているのに対し、海外への不動産投資の現状についてはどのようにお考えですか。たとえば東南アジアと欧米では、投資先としての性質が異なるように思いますが。
清水: 海外への不動産投資は、短期資金と長期資金でも性質が異なります。年金積立金を運用するGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が行っているような長期投資は、その国の政治的安定を重視します。東南アジアの国々は人口増加や経済成長が期待できますが、政情不安や建設不祥事などがしばしば投資リスクとなります。そのため長期資金はヨーロッパや米国など、より安定した国に配分されやすい傾向があります。一方、日本は少子高齢化が進むものの、政治が比較的安定していて強い規制もないため、海外資金が集まりやすいのです。海外からの投資を抑制しようという議論がありますが、市場経済の原則に反する不合理な判断だと思います。
川除: 海外からの対日投資を盛んに誘致している政策や、縮小していく日本経済の将来を考えると、抑制論には少々矛盾を感じますね。
清水: 東南アジアの国々は、日本が経験してきた産業構造転換や都市化のプロセスを猛スピードで進めています。ただし各国の法規制、制度、公共規制権限によって都市開発の進め方は大きく異なります。日本の官民連携による都市再生モデルがそのまま適用できるわけではありません。土地所有者や自治体との交渉、民間参入を促す機能が不足しており、建設途中のプロジェクトが破綻するリスクもあります。
都市のビッグデータを活用し、不動産情報を高度化
川除: 海外の不動産市場の状況から、日本の立ち位置と今後の動向が見えてきました。次に後半のテーマである不動産DXについて伺いたいと思います。不動産市場におけるビッグデータは、どんな可能性を秘めているとお考えでしょうか。
清水: 戦後、焼け野原から復興に乗り出した日本は、国土の均衡ある発展を目指し、均質な都市整備を進めました。その結果、日本中のどの都市も一定レベルのインフラを備えたものの、その多くが個性を失い、画一的な印象を与えるようになってしまったのは否めません。人口が減少に転じ、個人の価値観が多様化した現代では、独自の魅力があり、かつ多様なニーズに応えられるまちでないと、住みたいと思う人が減り存続しにくくなるでしょう。では逆に人々はまちや住まいをどのように選べばいいのか。そんな時に役立つのが都市のビッグデータです。情報が溢れる時代に人々が正しい選択をするためには、都市データを活用した不動産情報の高度化が不可欠です。
川除: 日建設計総合研究所は、清水先生監修のもと「Walkability Index」を開発しました。ある不動産が立地する地点から徒歩圏で到達できる範囲に、アメニティ(近くにあるとうれしい施設)がどれだけ集積しているかを100点満点で評価するこの指標は、まさに人々のまち選び、住まい選びを支援するツールです。
清水: 「Walkability Index」の開発目的は、不動産情報の“民主化”でしたよね。個人のライフスタイルやニーズに合わせて住みやすい場所をスコア化し、地図上で可視化するから、専門知識がない人でも自身に最適な情報を理解し、適切な選択ができるようになる点が画期的です。住宅やオフィス選びだけでなく、バリアフリー評価やまちづくりなどにも活用できる。人々の行動変容を促し、社会全体に貢献する可能性を秘めたツールだと思います。
川除: ありがとうございます。では不動産DXを加速させているAIについてはいかがですか。
清水: 戦後、焼け野原から復興に乗り出した日本は、国土の均衡ある発展を目指し、均質な都市整備を進めました。その結果、日本中のどの都市も一定レベルのインフラを備えたものの、その多くが個性を失い、画一的な印象を与えるようになってしまったのは否めません。人口が減少に転じ、個人の価値観が多様化した現代では、独自の魅力があり、かつ多様なニーズに応えられるまちでないと、住みたいと思う人が減り存続しにくくなるでしょう。では逆に人々はまちや住まいをどのように選べばいいのか。そんな時に役立つのが都市のビッグデータです。情報が溢れる時代に人々が正しい選択をするためには、都市データを活用した不動産情報の高度化が不可欠です。
川除: 日建設計総合研究所は、清水先生監修のもと「Walkability Index」を開発しました。ある不動産が立地する地点から徒歩圏で到達できる範囲に、アメニティ(近くにあるとうれしい施設)がどれだけ集積しているかを100点満点で評価するこの指標は、まさに人々のまち選び、住まい選びを支援するツールです。
清水: 「Walkability Index」の開発目的は、不動産情報の“民主化”でしたよね。個人のライフスタイルやニーズに合わせて住みやすい場所をスコア化し、地図上で可視化するから、専門知識がない人でも自身に最適な情報を理解し、適切な選択ができるようになる点が画期的です。住宅やオフィス選びだけでなく、バリアフリー評価やまちづくりなどにも活用できる。人々の行動変容を促し、社会全体に貢献する可能性を秘めたツールだと思います。
川除: ありがとうございます。では不動産DXを加速させているAIについてはいかがですか。
AIが業務を劇的に効率化し、人間の創造性を引き出す
清水: 現在、不動産DXは現状を可視化する“ナウキャスティング”の段階にあります。そして次のフェーズとして期待されているのが、AIを駆使した“フォアキャスティング”、つまり将来予測です。他分野ではすでに予測技術が社会の最適化に貢献しています。電力需要を高い精度で予測してエネルギー供給を効率化したり、新型コロナウイルスの感染者数を予測して医療リソースを最適に配分したりといった事例がその代表です。不動産・都市開発の分野では、将来の人口動態やライフスタイルの変化を予測することで、需要に見合った無駄のない開発や、効率的なインフラ維持管理が可能になるでしょう。
川除: 未来を予測する力は、都市経営のリスクを低減し、持続可能な成長を実現するための鍵となりそうですね。
清水: でも正確な予測技術を実現するには、正確な情報生産が不可欠です。土地情報はまだ半分程度しか公共座標や権利情報が紐付けられていません。建物の情報生産はさらに遅れています。建物の維持管理費予測など、将来を見据えた情報が不足しており、BIM(Building Information Modeling)のような3D設計技術による部材情報の記録と普及が喫緊の課題です。BIMと部材価格情報を連携させることで、建築費高騰の要因分析や将来予測の精度向上に繋がると考えています。
川除: BIMの普及は、建築業界のDXを大きく推進するでしょうね。先生は常々、人間が嫌がる単純作業はAIに任せるべきだとおっしゃっています。AIによる自動設計は、人間の創造性をどう引き出し、組織運営や働き方にどのような変革をもたらすのでしょうか。
清水: 建築設計における多くの無駄なボリューム提案作業は、自動設計で代替できます。これによって人間はより創造的な仕事に集中できるようになります。AIと人間は、それぞれが得意なことを分担すべきです。公平性や効率性を重視する業務をAIに任せ、人間は感情や個別事情を考慮する、より本質的な業務に集中すれば、組織運営は円滑になり、従業員の満足度も向上します。
川除: 行政の建築確認申請なども、AIが定型的なチェックを担い、人間は複雑な判断に集中する分業が進むことでDXが推進されますね。
清水: DX推進には、組織がAIを柔軟に受け入れ、活用の仕組みをしっかり作ることも重要です。AIは人間の話し相手や秘書業務の代行など、その応用範囲を広げており、今後も予測不能な速度で進化し続けるでしょう。人間とAIが共存する時代を迎え、あらゆる業界の働き方がドラスティックに変わりそうですね。
川除: 清水先生、本日は「不動産市場の展望と不動産DXの未来戦略」に関して、有益な意見交換、洞察をありがとうございました。ビッグデータやAIなどの情報技術の進化は未だ黎明期です。まちづくりや不動産DXの高度化に向けて、今後とも産官学連携による各々の強みを活かした先進的な取り組み/挑戦/協働が社会的に重要になると考えます。
川除: 未来を予測する力は、都市経営のリスクを低減し、持続可能な成長を実現するための鍵となりそうですね。
清水: でも正確な予測技術を実現するには、正確な情報生産が不可欠です。土地情報はまだ半分程度しか公共座標や権利情報が紐付けられていません。建物の情報生産はさらに遅れています。建物の維持管理費予測など、将来を見据えた情報が不足しており、BIM(Building Information Modeling)のような3D設計技術による部材情報の記録と普及が喫緊の課題です。BIMと部材価格情報を連携させることで、建築費高騰の要因分析や将来予測の精度向上に繋がると考えています。
川除: BIMの普及は、建築業界のDXを大きく推進するでしょうね。先生は常々、人間が嫌がる単純作業はAIに任せるべきだとおっしゃっています。AIによる自動設計は、人間の創造性をどう引き出し、組織運営や働き方にどのような変革をもたらすのでしょうか。
清水: 建築設計における多くの無駄なボリューム提案作業は、自動設計で代替できます。これによって人間はより創造的な仕事に集中できるようになります。AIと人間は、それぞれが得意なことを分担すべきです。公平性や効率性を重視する業務をAIに任せ、人間は感情や個別事情を考慮する、より本質的な業務に集中すれば、組織運営は円滑になり、従業員の満足度も向上します。
川除: 行政の建築確認申請なども、AIが定型的なチェックを担い、人間は複雑な判断に集中する分業が進むことでDXが推進されますね。
清水: DX推進には、組織がAIを柔軟に受け入れ、活用の仕組みをしっかり作ることも重要です。AIは人間の話し相手や秘書業務の代行など、その応用範囲を広げており、今後も予測不能な速度で進化し続けるでしょう。人間とAIが共存する時代を迎え、あらゆる業界の働き方がドラスティックに変わりそうですね。
川除: 清水先生、本日は「不動産市場の展望と不動産DXの未来戦略」に関して、有益な意見交換、洞察をありがとうございました。ビッグデータやAIなどの情報技術の進化は未だ黎明期です。まちづくりや不動産DXの高度化に向けて、今後とも産官学連携による各々の強みを活かした先進的な取り組み/挑戦/協働が社会的に重要になると考えます。