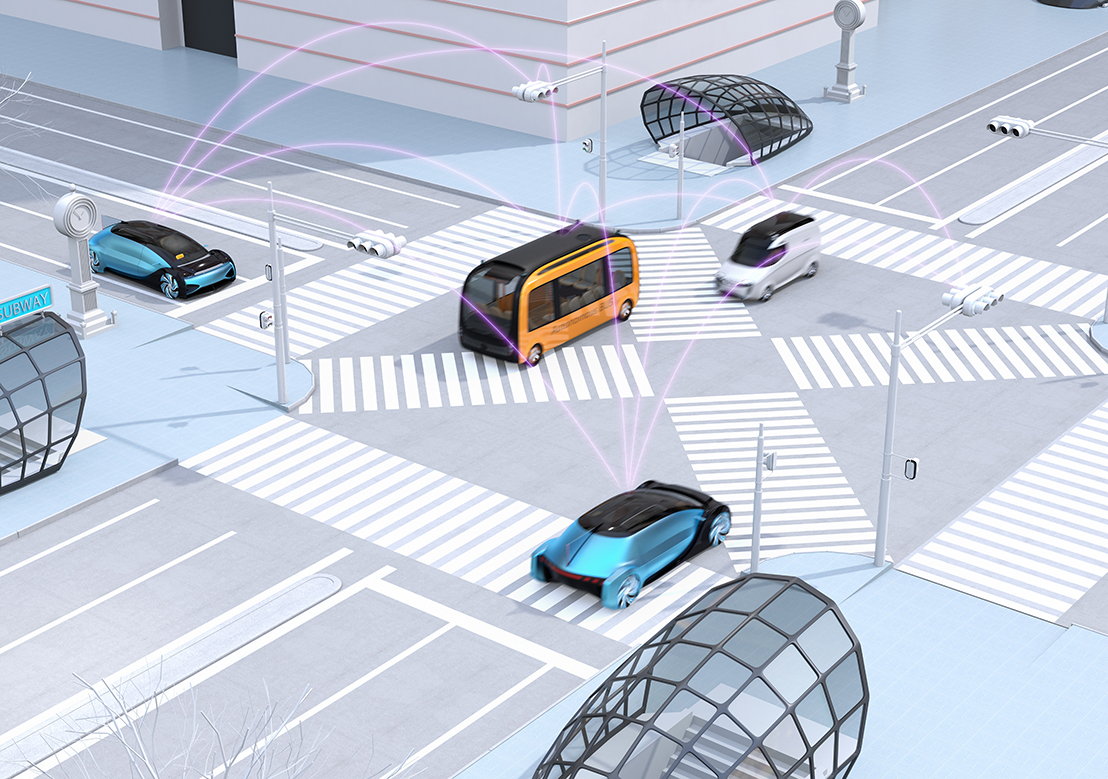
NSRIの「スマートTODi ラボ」では、毎月ゲストスピーカーをお呼びして特定のテーマについて所員との意見交換を行うテーマ・セッションを開催しています。ここでは、昨年10月に開催したセッションの概要をご紹介します。
全国でHELLO CYCLINGを中心とするシェアモビリティ事業を展開しているOpenStreet社の久冨さんにご参加いただきました。久冨さんはさいたま市のスマートシティ関連事業でNSRIともお付き合いのある方です。
冒頭、「我々は単にシェアサイクル事業を行うだけでなく、モビリティを切り口に様々な取り組みを進めています」という一言から始まりました。都市のオペレーションシステムすなわちインフラとしての役割、そして移動の概念を変えることにより都市を変える、そんな役割を担っていきたい、と語られました。
プレゼンテーションのなかでは、「〇〇×マイクロモビリティ」として多様な展開が紹介されました。〇〇としては、公共交通、エネルギー、防災、データなど。確かに、シェアモビリティの走行経路を分析することにより、公共交通との接続向上やまちの回遊性の向上など、都市空間を改善するうえでの示唆を得ることが出来そうです。また、シェアサイクルやシェアEV車の動力源は電力のため、災害時には「走る蓄電池」として電力を適切な場所にデリバリーすることも可能となり、シェアモビリティを整備することが都市の強靭化にも繋がりそうです。2021年の10月に首都圏で地震が発生した際、鉄道が運休する中で災害時の帰宅困難者の足となったことは記憶に新しいところです。
後半はNSRI所員とのディスカッションが行われました。今後の自動運転技術の普及に応じてどのようなビジネス展開が想定されうるか、という所員からの質問に対して「その頃には道路の形、車の形、移動や所有に関する概念も大きく変わっている可能性があります」と述べ、それぞれの技術の進展に応じてその時代に求められる移動の形の提案、それに応じたマイクロモビリティの形を追求していきたい、というビジョンを示されました。
コロナ禍におけるライフ・ワークスタイルの変化を背景として、ラストワンマイルへの対応可能なモビリティの重要性はますます増しています。そして、移動だけでなく様々な価値に繋げていくOpenStreet社のアプローチは、今後の街づくりを考えるうえで新たなインフラとしての可能性を強く感じました。
冒頭、「我々は単にシェアサイクル事業を行うだけでなく、モビリティを切り口に様々な取り組みを進めています」という一言から始まりました。都市のオペレーションシステムすなわちインフラとしての役割、そして移動の概念を変えることにより都市を変える、そんな役割を担っていきたい、と語られました。
プレゼンテーションのなかでは、「〇〇×マイクロモビリティ」として多様な展開が紹介されました。〇〇としては、公共交通、エネルギー、防災、データなど。確かに、シェアモビリティの走行経路を分析することにより、公共交通との接続向上やまちの回遊性の向上など、都市空間を改善するうえでの示唆を得ることが出来そうです。また、シェアサイクルやシェアEV車の動力源は電力のため、災害時には「走る蓄電池」として電力を適切な場所にデリバリーすることも可能となり、シェアモビリティを整備することが都市の強靭化にも繋がりそうです。2021年の10月に首都圏で地震が発生した際、鉄道が運休する中で災害時の帰宅困難者の足となったことは記憶に新しいところです。
後半はNSRI所員とのディスカッションが行われました。今後の自動運転技術の普及に応じてどのようなビジネス展開が想定されうるか、という所員からの質問に対して「その頃には道路の形、車の形、移動や所有に関する概念も大きく変わっている可能性があります」と述べ、それぞれの技術の進展に応じてその時代に求められる移動の形の提案、それに応じたマイクロモビリティの形を追求していきたい、というビジョンを示されました。
コロナ禍におけるライフ・ワークスタイルの変化を背景として、ラストワンマイルへの対応可能なモビリティの重要性はますます増しています。そして、移動だけでなく様々な価値に繋げていくOpenStreet社のアプローチは、今後の街づくりを考えるうえで新たなインフラとしての可能性を強く感じました。
[講師]
OpenStreet 株式会社 マーケティング統括 データサイエンス課
久冨 宏大 氏
OpenStreet 株式会社 マーケティング統括 データサイエンス課
久冨 宏大 氏



